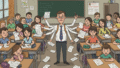「授業は先生が進めるもの」——そんな常識が、今静かに変わり始めています。全国の一部の小学校では、子どもたち自身が授業の進行役となり、課題の設定から学習方法の選択、発表までを自ら行う取り組みが始まっています。愛知県にある藤山台小学校の事例をご紹介します。
事例:藤山台小学校のクラウド活用型授業
藤山台小学校では、Google ClassroomやJamboardなどのクラウドツールを活用し、子どもたちが授業の流れを自ら構築するスタイルを確立しています。
- 教科ごとにGoogle Classroomを設置し、授業開始と同時に子どもが自分でアクセス
- 「めあて」「ながれ」「なかみ」などの授業情報はすべてクラウド上に集約
- 学びの記録はポートフォリオとして保存され、いつでも振り返り可能
教師は教室を俯瞰しながら、子どもたちの学び方や協働の様子を観察し、必要に応じて声をかけるだけ。まさに“教える”から“支える”への転換です。
学び方を子どもが選ぶ授業設計
藤山台小では、学び方そのものを子どもが選択できるようにしています。たとえば国語の授業では、提案文の構造をJamboardで可視化し、1回目は全員で作成、2回目は個人で挑戦。こうした段階的な設計により、子どもたちは「他者の学びを参考にしながら、自分のスタイルを確立する」ことを学びます。
- ノート・チャット・スライドなど、記録方法も子どもが自由に選択
- Googleカレンダーで宿題や小テストの予定を管理する児童も
- 自宅でGoogle Meetを使って友達と宿題を進めるケースも報告
このように、学びの手段・記録・協働の方法までを子どもが自律的に選ぶことで、学習への主体性が自然と育まれています。
情報活用力を育てる「情報の時間」
藤山台小では、アウトプットの質と量を高めるために「情報活用力」を育てる時間を設けています。課題設定・情報収集・整理分析・発信という一連の流れを体系的に教えることで、どの教科でも質の高いアウトプットが可能になります。
- Googleスプレッドシートで仮説検証を行う
- Google Chatで意見交換やフィードバックを実施
- 成果物はクラウド上に保存し、他者と共有・比較が可能
このような環境では、教師が全体指示を出す場面はほとんどなく、子どもたちが自ら動き、考え、発信する授業が日常化しています。
教師の役割は“俯瞰と応援”
藤山台小の教師は、授業中に教室を歩きながら「誰と学んでいるか」「どう学んでいるか」を観察します。直接教えるのではなく、子どもたちの学びの流れを見守り、必要なタイミングで声をかけるスタイルです。
クラウド環境により、子ども同士の学び方が可視化されるため、優れた学習方法が自然と広がり、教室全体の学びの質が底上げされていきます。
なぜこのような授業が可能なのか?
- 「主体的・対話的で深い学び」が学習指導要領に明記
- GIGAスクール構想による1人1台端末の整備
- 教師の役割が「教える」から「支える」へと変化
まとめ
子どもたちは、自分で考え、選び、学ぶ力を持っています。その力を引き出すには、「任せる勇気」と「見守る覚悟」が必要です。学校でも家庭でも、「主体的な学び」を育てる環境づくりが、これからの教育の鍵になるでしょう。

子供たちに授業をさせるって凄く良い発想だよね!先生がやるよりも興味を持って楽しく進められそう。先生は支援に回るので、生徒が慣れてくれば負担も軽くなりそうだし、本来そういう役割が正しいのかも。想像するだけでワクワクするよね。